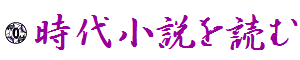大わらんじの男(4)
| 江戸で物価高が続き、それに伴い米価安となったことで旗本や御家人の暮らしが窮乏していきます。吉宗は、倹約に力を入れ消費拡大を抑える政策で乗り切ろうとしますが、思うように物価を安定させることができず苦心するのでした。 |
PR
主な登場人物
あらすじ
江戸で消費生活が拡大することで、諸色高の米価安の状況が続き、武家の窮乏に拍車がかかっていました。
これに対し、吉宗は倹約の布令を繰り返し、大岡忠相にも、消費拡大の傾向を阻止する施策を行わせようとします。そんな時、目安箱に山下幸内が投書します。投書には、新井白石の通貨収縮政策により米価が下落していること、吉宗の倹約令が経済を縮小させていることが書かれており、鷹野も控えるべきだと書かれていました。
吉宗はこの投書に感心する一方、鷹野は旗本・御家人を鍛え直す必要性からやめるつもりはありませんでした。
また、吉宗は年貢の徴収方法も改正します。従来の作柄に応じて年貢量を定める検見取(けみどり)法では、地方役人が賄賂を受け取り徴収量を少なくする不正が見られたことから、作柄に関係なく一定量の年貢を徴収する定免法に切り替える方針を決めるのでした。
読後の感想
第4巻では、吉宗が本格的に改革に乗り出します。
幕府財政がひっ迫する中、吉宗は倹約により乗り切ろうと試みます。しかし、倹約は幕府の支出を切り詰めるだけでなく、経済全体を落ち込ませる結果となりました。
江戸時代は、米を税として徴収する一方、貨幣経済が発達していく時代でもあり、それが幕府財政の辻褄を合わせるのに難儀する理由でした。米が豊作となっても、旗本や御家人が受け取る米の量は変わらない一方、市中では米価が下落し、米を換金すると収入が減るという矛盾が生じます。不作の年は、その逆となって米価が上がり江戸市民の暮らしが厳しくなります。
それゆえ、米価の安定が武士にもそれ以外にも望ましいことなのですが、なかなか思うように米価は安定せず、吉宗は苦心しました。
吉宗は、家臣、町人、農民に対して理不尽な行為は行わず、将軍の権威を高めようとすることもありませんでした。だから、名君と言われているのですが、米本位制経済と貨幣経済が同居する江戸時代中期の経済政策については結果を出せませんでした。
第4巻では、この辺りの吉宗の苦悩が読みどころとなっています。
| 大わらんじの男(4)-津本陽 |
| 取扱店(広告) |