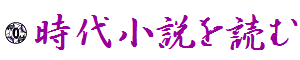大わらんじの男(3)
| 早逝した家継の跡を継ぎ、吉宗は8代将軍になりました。譜代を登用し新参との対立を解消したり、幕府巡検使が諸大名の接待を受けることを禁止するなど、着々と幕政を改革していきます。一方で、些細な失敗には寛容な態度を見せ、吉宗の評判が高まっていくのでした。 |
PR
主な登場人物
あらすじ
正徳5年(1715年)5月。吉宗は日光に参詣し、東照宮で家康百回忌法要に参列しました。
幼き7代将軍家継の後見を誰にするか。幕府内で議論が交わされた結果、吉宗に白羽の矢が立ちます。彼は後見をためらったものの、血統面で家康に近いことから引き受け、江戸城二の丸御殿に住まうこととなりました。
しかし、間もなく家継が幼くして亡くなり、吉宗が8代将軍となるのでした。
吉宗は、幕府巡検使が諸大名に接待を受けていることを問題視していたため、これを禁止。譜代の幕臣を優遇する方針も打ち出し、譜代と新参の対立関係の解消にも努めました。
また、身分の低い者の些細な失敗は強く責めず、幕府内外の吉宗の評判は高まっていくのでした。
読後の感想
いよいよ吉宗が8代将軍となり、享保の改革が始まります。
享保の改革は倹約を中心としたものでしたが、下々に対して厳しい態度を取らない吉宗は庶民から人気がありました。彼は鷹狩を好み、よく出かけていましたが、そこで御小人が担いでいた鉄砲の先が額にあたっても咎めなかったという話も本作に登場します。
一方で、過去の貨幣改鋳により金銀の価値が下がったことによる物価高には悩まされていました。借金を返せなくなった者を奉行所に訴える債権者が増え、これに対応するのが難しくなったことから、相対済し令を発し、奉行所が裁断しない方針を取ります。しかし、相対済し令により借金を返済しない者が出てき、町奉行所が借金返済を厳命する裏判出しという制約措置を講ずるようになりました。
5代将軍綱吉の時代に貨幣経済が発展し、米本位制経済の矛盾が生じ始めた享保の時代に吉宗がどう対応していくのかも第3巻の読みどころです。
| 大わらんじの男(3)-津本陽 |
| 取扱店(広告) |