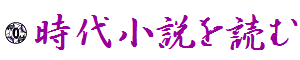峠の群像(4)
| 赤穂藩の取り潰しが決まり、大野九郎兵衛は、藩札の清算に追われるも、石野七郎次の才覚により何とか乗り切ります。藩士たちは、これからどうするのか。お家再興を目指すのか、主君の仇討ちをするのか。筆頭家老の大石内蔵助は、仇討ちを望む藩士たちをまとめ上げ、吉良邸に討ち入るのでした。 |
PR
主な登場人物
- 大石内蔵助
- 大野九郎兵衛
- 堀部安兵衛
- 堀部弥兵衛
- 片岡源五右衛門
- 安井彦右衛門
- 藤井又左衛門
- 原惣右衛門
- 磯貝十郎左衛門
- 矢頭長介
- 矢頭右衛門七
- 高田郡兵衛
- 小山源五左衛門
- 吉田忠左衛門
- 小野寺十内
- 石野七郎次
- 大石主税
- 柳沢吉保
- 町子
- 吉良上野介
- 小林平八郎
- 清水一学
- 近松門左衛門
- 綿屋善右衛門
あらすじ
浅野内匠頭が吉良上野介に斬りつけた事件で取り潰しが決定した赤穂藩では、領内で発行していた藩札の清算に追われていました。
藩札と貨幣の交換率をどうするかを大野九郎兵衛が試算し、石野七郎次が藩内に残っている財産を調べるも、藩札と交換できるだけの貨幣が足りません。それでも、浜方に貸し付けた五千両の回収に目途をつけ、困難する藩札の清算を乗り切ります。
しかし、藩士たちは、浅野家の再興を幕府に訴えるか、赤穂城に籠城するかで揉め始めます。大野九郎兵衛は、お家再興のために働くも、実現する見込みは乏しい状況。一方、筆頭家老の大石内蔵助は、浅野内匠頭の仇を討つため、一部の藩士をまとめ上げていきます。
浅野家が断絶した後、赤穂には永井家が入りました。石野七郎次は、永井家の許しを得て、数十人の旧藩士とともに赤穂の塩業を存続させます。そして、自分は武士をやめ、商人になる道を選ぶのでした。
読後の感想
『峠の群像』の最終巻です。
赤穂藩の取り潰しが決定し、藩士全員が収入を断たれることになりました。ここから、大石内蔵助が旧藩士たちとともに吉良邸に討ち入るために計画を練っていくのが、よくある忠臣蔵の展開ですが、本作では、そこにはあまり紙数を割いていません。
藩士たちのその後の生活はどうなるのか、そちらに多くの紙数が割かれているのが本作の特徴と言えるでしょう。
大石内蔵助とともに仇討ちに参加する決意をした藩士の中には、途中で脱盟する者が何人もいました。それを単なる裏切りと考えるべきではありません。討ち入りまでの生活費をどうするのかという現実的な問題に直面すると、脱盟するのは仕方がないことです。また、旧藩士の中には、脱盟することもできず自害する者もいました。
仇討ちに参加しなかった旧藩士の中には、塩業により生計を立てる者もいましたし、赤穂藩とは関わりなく生活する道を選んだ者もいました。それら旧藩士たちも、やがて仇討ちの後に苦労することになります。世間は、大石内蔵助らの討ち入りに歓喜する一方、討ち入りに加わらなかった旧藩士たちに冷たい視線を送ります。旧藩士たちの生活再建に尽力してきた人々は、肩身の狭い思いをするのでした。
一方、討ち入りに参加した旧藩士たちも、一枚岩ではありませんでした。討ち入りという目標は同じでも、何のために討ち入りをするのか、その目的は人それぞれです。浅野内匠頭の無念を晴らして武士らしく散ろうとする者、仇討ちを成功させて他藩に取り立てられるのを願う者、仇討ちがお家再興につながると考える者。
これら目的の異なる旧藩士をまとめ上げる大石内蔵助の苦悩が、本作の読みどころと言えます。
本作は、最初から最後まで、経済の視点で元禄という時代を描いています。経済と文化が花開いた元禄時代。戦乱も終わり、生類憐みの令が出され、殺生が禁じられていた平和の時代に赤穂浪士の討ち入りが起こったことに庶民は大はしゃぎします。
しかし、赤穂事件に関わった者たちは、皆、不幸になっています。赤穂浪士は全員死罪。被害者である吉良家も取り潰し。やがて、事件は忘れられていきます。
| 峠の群像(4)-堺屋太一 |
| 取扱店(広告) |