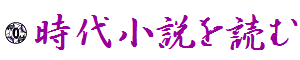市塵(下)
| 朝鮮通信使の迎接に就いた新井白石は、将軍の呼称を日本国王に改めることや御三家の相伴廃止といった通信使改革案を実行に移します。そして、通信使迎接の後は、荻原重秀によって劣化した貨幣の質を元に戻すため金銀貨の改鋳案をまとめるのでした。 |
PR
主な登場人物
あらすじ
正徳元年(1711年)10月17日。新井白石は、徳川家宣の命で川崎駅まで朝鮮通信使の一行を迎えます。
白石は、将軍の日本国大君の呼称を日本国王に改めること、御三家の相伴を廃止することといった通信使改革案を実行に移そうとするものの、各方面から反発を受けます。
朝鮮通信使迎接を終え、職を辞そうとした白石でしたが、家宣に慰留され、辞職を思いとどまります。
その後の白石は、荻原重秀によって行われた貨幣改鋳により、小判や銀貨の質が劣化したことに対応します。貨幣改鋳で私腹を肥やしていた荻原重秀を罷免するとともに金銀貨を旧にもどすべく改鋳の具体策を練り始めます。
白石が、貨幣改鋳案を作成する中、将軍家宣が病死。幼い家継が7代将軍となりました。そして、白石は、家宣の遺言により、金銀改鋳に関する意見書「改貨議」の執筆にとりかかります。
しかし、白石の改鋳案が漏れると、これまでより物価が上昇することになるのでした。
読後の感想
『市塵』の最終巻です。新井白石の朝鮮通信使の迎接と貨幣改鋳が下巻の読みどころですが、徳川吉宗が8代将軍に就任して以降の白石の方が印象に残ります。
江戸時代は徳川家が政治を担っていましたが、将軍の代替わりは、現代の政権交代に近いものがあります。これまで、幕府の要職を務めていた者が、将軍が代わったことで失脚し、その後どうなったのか、誰にも意識されることなく世を去って行きます。5代将軍綱吉の下で権勢を振るった柳沢吉保は、家宣が将軍となった後に失脚。そして、間部詮房と新井白石が政治の舞台に躍り出ました。
しかし、家宣が病死し、その後を継いだ家継も早世すると、間部詮房も新井白石も、政治の中枢から去ることになります。幕府政治に深く関わった人物のその後があまり知られていないのは、将軍が交代するとお役御免になり、表舞台から姿を消していたからなのでしょう。
幕府政治から身を引いた後の白石は、町で暮らす一介の儒者に戻ります。読者は、最後の最後で、本作のタイトルの意味を知ることになります。
| 市塵(下)-藤沢周平 |
| 取扱店(広告) |